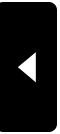北アルプスの峰々は今シーズン初冠雪 高山市奥飛騨温泉郷
2023年10月7日

ここ数日高山市内は冷たい雨が降りましたが、北アルプスの高い峰々では雪が降りました。

今日は青空が広がり、奥飛騨温泉郷 新穂高温泉からは初冠雪した峰々を見ることができました。
いつもの蒲田川にかかる穂高橋から

下界はこれから紅葉の季節を迎えますが、山の上はすでに真冬の様相です。

穂高橋からは3座の3000mオーバー峰が、車から降りてわずか数歩で仰ぎみることができる、超〜ッ!お気軽絶景スポットです。

中尾高原の色づくナナカマド
北アルプスの峰々に雪が降ると、冬用タイヤに交換するタイミングを思案し始める比呂池です。

ここ数日高山市内は冷たい雨が降りましたが、北アルプスの高い峰々では雪が降りました。

今日は青空が広がり、奥飛騨温泉郷 新穂高温泉からは初冠雪した峰々を見ることができました。
いつもの蒲田川にかかる穂高橋から

下界はこれから紅葉の季節を迎えますが、山の上はすでに真冬の様相です。

穂高橋からは3座の3000mオーバー峰が、車から降りてわずか数歩で仰ぎみることができる、超〜ッ!お気軽絶景スポットです。

中尾高原の色づくナナカマド
北アルプスの峰々に雪が降ると、冬用タイヤに交換するタイミングを思案し始める比呂池です。