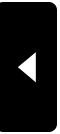御嶽山からのご来光 & 夕陽に染まる御嶽山 を撮影
2023年1月14日

ここ連日いい天気が続いたので、県道441号・御嶽パノラマライン(険道とも言う!・下呂市小坂町)へ行ってきました。朝2回・夕1回

日の出の時刻の7時になりましたが、標高が高いので、ご来光はまだまだ先です。

黄:今日の太陽
シアン:冬至
緑:春分・秋分

7時50分、剣ヶ峰の右手からご来光です。

カラ松林越しに太陽を写してみました。左手奥には御嶽山が見えます。
おことわり:ブログの幅が600pxしかないので、パノラマ画像は右回転90度でアップしています。パソコン・スマホを左回転90度してご覧ください。

朝は逆光ですが、次第に順光になります。

「日本一の溶岩流」をパノラマ撮影

雪が積もり白いので、ホワイトバランスを調整するとピンクが鮮やかに出ます。
夜明け前パノラマラインへ向かう時、朝日町(標高900m付近)の気温はマイナス10度近くまで下がり、標高の更に高いパノラマラインの気温が心配でした。
ところが鈴蘭峠(標高1210m)を通過すると気温が上がり?だし、パノラマライン(標高1400m付近)ではマイナス5度程度と、寒気はより低い場所に集まることが体感できました。
今回はたまたまこういった天気だったのですが、パノラマラインではマイナス15度以下になることもよくあります。人も車もカメラも完璧な積雪&防寒対策をして向かいましょう。
パノラマラインから下りて、朝日町内での撮影はこちら

ここ連日いい天気が続いたので、県道441号・御嶽パノラマライン(険道とも言う!・下呂市小坂町)へ行ってきました。朝2回・夕1回

日の出の時刻の7時になりましたが、標高が高いので、ご来光はまだまだ先です。

黄:今日の太陽
シアン:冬至
緑:春分・秋分

7時50分、剣ヶ峰の右手からご来光です。

カラ松林越しに太陽を写してみました。左手奥には御嶽山が見えます。
おことわり:ブログの幅が600pxしかないので、パノラマ画像は右回転90度でアップしています。パソコン・スマホを左回転90度してご覧ください。

朝は逆光ですが、次第に順光になります。

「日本一の溶岩流」をパノラマ撮影

雪が積もり白いので、ホワイトバランスを調整するとピンクが鮮やかに出ます。
夜明け前パノラマラインへ向かう時、朝日町(標高900m付近)の気温はマイナス10度近くまで下がり、標高の更に高いパノラマラインの気温が心配でした。
ところが鈴蘭峠(標高1210m)を通過すると気温が上がり?だし、パノラマライン(標高1400m付近)ではマイナス5度程度と、寒気はより低い場所に集まることが体感できました。
今回はたまたまこういった天気だったのですが、パノラマラインではマイナス15度以下になることもよくあります。人も車もカメラも完璧な積雪&防寒対策をして向かいましょう。
パノラマラインから下りて、朝日町内での撮影はこちら
2023/01/15