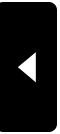飛騨高山市民花火大会 人生は逆風だけど花火撮影は順風で(1/2)
2022年8月7日

「飛騨高山市民花火大会」が、昨夜(8月6日)開催されました。
(主催:岐阜新聞社・岐阜放送)

打ち上げ地点は、以前は宮川河畔でしたが、今回はアルプス展望公園スカイパークです。

スカイパークは高山のどこからでも見えるので、撮影場所をどこにするのか迷いました。

花火と高山の町をいっしょに写したいので、当初は城山公園または北山公園を検討していました。

花火撮影の基本は「風上から撮る」です。
煙が自分の方へ吹いてくると、どんな高性能カメラでもお手上げです。

比呂池のカメラマン人生はいつも逆風ですが、花火撮影だけは順風と行きたいところです。

天気予報は「南または南西の風 秒速3m」で、北山公園は煙が流れる方向だったのでパス。

城山公園は、煙が右へ流れますが、西風になると微妙?でした。

そんな訳で、打ち上げ地点の南側で探した結果、苔川(すのり)玄興寺橋の下流付近を撮影場所としました。

苔川の水は少なく、撮ってくださいと言わんばかりに、水面から出た平らな石が並んでいます。
川の左岸は電柱や電線がなく、川の流れる方向がスカイパークを向いており川面に反射する花火も画面に入れることができました。

2年間撮れなかった分、たくさん撮ってしまい、画像処理がおいつきません。
後半の花火は次回アップします。
お断り:画像は複数枚の画像をPhotoshopで合成処理しています。

「飛騨高山市民花火大会」が、昨夜(8月6日)開催されました。
(主催:岐阜新聞社・岐阜放送)

打ち上げ地点は、以前は宮川河畔でしたが、今回はアルプス展望公園スカイパークです。

スカイパークは高山のどこからでも見えるので、撮影場所をどこにするのか迷いました。

花火と高山の町をいっしょに写したいので、当初は城山公園または北山公園を検討していました。

花火撮影の基本は「風上から撮る」です。
煙が自分の方へ吹いてくると、どんな高性能カメラでもお手上げです。

比呂池のカメラマン人生はいつも逆風ですが、花火撮影だけは順風と行きたいところです。

天気予報は「南または南西の風 秒速3m」で、北山公園は煙が流れる方向だったのでパス。

城山公園は、煙が右へ流れますが、西風になると微妙?でした。

そんな訳で、打ち上げ地点の南側で探した結果、苔川(すのり)玄興寺橋の下流付近を撮影場所としました。

苔川の水は少なく、撮ってくださいと言わんばかりに、水面から出た平らな石が並んでいます。
川の左岸は電柱や電線がなく、川の流れる方向がスカイパークを向いており川面に反射する花火も画面に入れることができました。

2年間撮れなかった分、たくさん撮ってしまい、画像処理がおいつきません。
後半の花火は次回アップします。
2022/08/08
お断り:画像は複数枚の画像をPhotoshopで合成処理しています。
タグ :飛騨高山市民花火大会花火