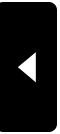飛騨の里「車田」の稲刈り 里山に広がる日本の原風景
2018年 9月22日

飛騨の里「車田」で稲刈りが行われました。

「車田」は、高山市松之木町と佐渡市に現存し、かつては伊勢神宮に献上するお米を作る水田として、車輪の形に苗を植えたので名づけられたと言われています。

飛騨の里は、飛騨各地から古い建物等を移築し、里山の中に昔の飛騨の暮らしを再現した集落博物館で、高山市松之木町の車田を復元してあります。



飛騨地方でも 稲刈り や 乾燥 は機械で行うところがほとんどで、貴重な手作業の 稲刈り や はさ掛け の様子を撮影できるのは、ここ飛騨の里だけではないでしょうか。

また、車田の横には白川郷から移築された合掌造りの旧西岡家がありシチュエーションは完璧、まるで◯十年前にタイムスリップしたかのような日本の原風景が広がっています。


飛騨の里「車田」で稲刈りが行われました。

「車田」は、高山市松之木町と佐渡市に現存し、かつては伊勢神宮に献上するお米を作る水田として、車輪の形に苗を植えたので名づけられたと言われています。

飛騨の里は、飛騨各地から古い建物等を移築し、里山の中に昔の飛騨の暮らしを再現した集落博物館で、高山市松之木町の車田を復元してあります。



飛騨地方でも 稲刈り や 乾燥 は機械で行うところがほとんどで、貴重な手作業の 稲刈り や はさ掛け の様子を撮影できるのは、ここ飛騨の里だけではないでしょうか。

また、車田の横には白川郷から移築された合掌造りの旧西岡家がありシチュエーションは完璧、まるで◯十年前にタイムスリップしたかのような日本の原風景が広がっています。